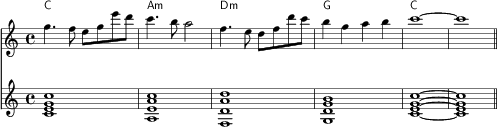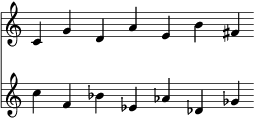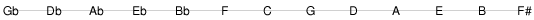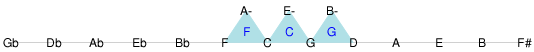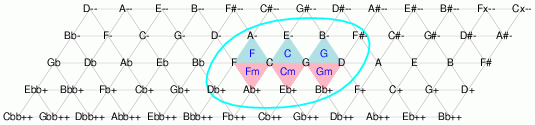純正律をはじめとする様々な音律に関する歴史や思想的背景を解説します。
当コラムでは皆様から音律に関する質問を受け付けております。「これが知りたい!」という疑問がある方は是非ご投稿下さい。それに答える形でコラムを連載することができたら,と思っております。
目次
玉木宏樹のコラム
ビブラートの正体について
私はヴァイオリン奏きなので,ビブラートをかけるのは絶対的な日常性なのだが,この,一見純正律とは相反するような奏法について考えてみたい。ただし,ビブラートの歴史や必然を述べている著作にはほとんど出合ったことがないし,大部分は自分の体験上の裏付けによっているということを前提にするので,私が間違った記述をしたり,または別の角度からの意見があったら,ぜひ,投稿するなり私のホームページの掲示板に書き込むなりしていただきたい。
「特権」としてのビブラート
さて,ビブラート(英語ではヴァイブレーション)は,ある音程を基音に,微妙なピッチの上下によって「ふるえ」を生じさせ,強弱等のエモーションを強調させる役割を担っている。現代の大人の演奏は,ソロの場合,歌でも音楽でもほとんど無自覚にビブラートをかける。古楽や小アンサンブルのコーラス,ブルガリア系のコーラス以外は,全く無自覚にビブラートをかけて歌うので,コーラスの場合,ハモることを全く度外視して悲惨な結果を招いている。大多数のママさんコーラスはもとより,プロと称している合唱団も総て,ハモるのが基本の「純正律」上から見ると死刑に値するほど勝手なビブラートをかけあって,何が何やら分からぬ騒音集団と成り果てている。
天国的な協和を目指す我が純正律音楽研究会に於ては,こういう騒音は退治してまわらなければならないのだけど,その代表者たる私・玉木がヴァイオリンを奏くと,ほとんどの場合,ビブラートをかけっ放しである。私がよく純正律のカラオケ・テープに合わせて奏く場合でも,バックはノンビラートなのにソロ・ヴァイオリンはビブラートをかけまくっている。そして当然,ビブラートをかけた瞬間の(譜面の)「たてわり」は明らかにハモってはいない。これはどういうことなんだ!結論から先に言ってしまおう。ビブラートをかけることができるのはソリストの特権なのである。
少し視点を変えよう。通常のクラシック楽器の場合,ほとんどはビブラートをかける。ただし,ハープやピアノ,ギター等,音が伸びない楽器はビブラートをかけられないし(遅い曲におけるギターを除く),そういう楽器の場合は音が伸びない部分で速いパッセージやアルペジオを多用する。この「速いパッセージ」は後ほど重要なテーマになるので覚えておいてほしい。
クラリネットの謎?
ところで,音が伸びてもビブラートをかけない楽器がある。それは,大部分のホルンとほとんどのクラリネットである。ホルンの場合,ソロよりも4人くらいのアンサンブルの方が効果的であり,その場合は,ノンビブラートで完全にハモらないと,吹いてる人達も聴いている方も非常な不快感に襲われる。ウェーバーの「魔弾の射手」の序曲のホルンが銘々ビブラートをかけたら,地獄に落ちた狼のような響きがするだろう。
そして,木管楽器では唯一,クラリネット。この楽器はもちろんビブラートがかけられないのではない。ベニー・グッドマンをはじめとしたジャズ・クラリネット奏者は,物の見事に魅惑的なビブラートをかけるのに,なぜクラシック奏者はかけないのだろう。私はこれに対する的確な答えをきいたことがない。多分,品がないという理由かもしれないが,それでは,オーボエやフルートは全く下品な楽器ということになる。
私の憶測にしか過ぎないが,クラリネットがノンビブラートなのは,実はクラリネットが一番新しい楽器であることの証拠のように思えてならない。
クラリネットは大体,1700年頃発明(というか古楽器の大改良)されており,種々の改良を経て,モーツァルトの後期の交響曲(特にNo.39)にも取り入れられ,また,モーツァルトの代表曲として,クラリネット協奏曲,クラリネット五重奏がある。モーツァルトの後期は,クラリネットと共にピアノフォルテのチェンバロ(ピアノの前身)も登場し,ベートーベンへと受け継がれ,音楽の在り方が激変する。
ところで今,古楽ブームがあり,モーツァルト・チューニングとして,今よりも約半音低い音程でのアンサンブルが流行っている。そのアンサンブルは,原則的にはソロ以外はノンビブラートである。
パガニーニ時代のヴァイオリンは,ソロでさえノンビブラートだったらしい。ヴァイオリンのビブラートが一世を風靡したのはサラサーテの登場以来といわれている。
昔気質の新人・クラリネット
さて,リード系の木管楽器の場合,オーボエもファゴットもどちらかといえば音程がふらつき易く,特にフルートは音程が安定しにくい。モーツァルトはフルートの曲も残しているが,内心,フルートは音程が悪いから嫌っていたようだ。ハモることを前提にしていた古典派の演奏で,オーボエやフルートをノンビブラートでハモるのはなかなか難しい。そこへさっそうと現れた新楽器クラリネットは,その音色のせいもあって,ノンビブラートでハモった時がすばらしく美しい。だから,一番よくハモる楽器として登場して以来,ずっとその伝統が受け継がれてきたのではないだろうか。
もともと音程の不安な複リード楽器はビブラートに頼るようになり,昔のようなハモりの響きが失われていったのが現代のオーケストラであり,その中にあって未だに頑固にハモりを主張して新しい楽器なのにコンサバになってしまったのは大変面白い。
話は変わり,ビブラートには2種類あるのはお分かりだろうか。たいていのビブラートは,確固とした基音の音程があり,その基音を中心に,上下に音程変化をさせる方法。弦楽器,フルート,方法論の特殊なものとしてビブラフォンやエレキピアノもこの部類。昔,ハモンドオルガンのビブラート用にレスリーというエフェクターがあったが,これは実は扇風機であり,羽の回転によりディレイのかかった音程変化が得られる。原理的にはビブラフォンと同様である。ところが,基音のないビブラートがもう一種類。それはブラス系のビブラートと人間の歌声のビブラート。これは確固とした基音はなく,ある幅で,基音と思われる音の周辺のをはっきりと音程変化させている。なかなか説明するのは難しいが,トロンボーンのようにスライド式の楽器のことを想像すると分かっていただけると思う。人間の歌声がまさにこの方法であり,オペラアリアのトリルなんか,ビブラートを激しくしただけのことであり,あまりビブラートとの違いははっきりしない。なんとなくビブラートの幅が多くなっただけのようでもある。
歌声のようなvln二胡奏法
ところで,同じ弦楽器でも中国の二胡という胡弓のビブラートはヴァイオリン族とは全く違い,歌のビブラートと同じように音程変化で表現する。二胡にはもともと指板がないので,安定した音程を作りにくいが,弦を深く押さえることによって音程は高くなる。だから二胡のビブラートは弦の押さえ方の強弱で表現する。ギターでいえばチョーキングであり,シタールも全く同じである。
私は自分のヴァイオリンで二胡風のビブラート奏法をするが,これは左手の一本指だけで演奏する。音程の上下関係でかけるビブラートはほとんど二胡風で,全く,ヴァイオリン的ではない。私はある時,ソプラノとのデュオの仕事があり,このビブラートを使ったところ,ソプラノが2人いるように聞こえた。ヴァイオリンが一番人間の声に似ていると言われるのには,このような演奏方法をしないと分からないのである。
ピアノと純正律
紅白でゴスペラーズが出て話題になり,急激にハモるコーラスが注目されだしている。私から見れば,ゴスペラーズも善し悪しで,1940年代の黒人ゴスペル・グループとは比較のしようもない段階である。でもハモるということはとても良いことで,純正律への一里塚である。テレビでも「ハモネプ」コーナーなどもやっており,ますますハモる系統が増えていくことだろう。
いま,アマチュアが熱い!
さて,2002年3月17日に横浜栄区の音楽協会によばれ,リリスホールで純正律のレクチャー・コンサートをやったが,ほぼ満員。しかも圧倒的な支持を受け熱い興奮が伝わってきた。アマチュア音楽愛好者の集まりだったが,コーラスの人も多かったため純正律に関する興味と関心は非常に高かった。一緒にステージに上がってくれた女声コーラスのプーラ・ボーチェは一切ビブラートもなく,あの懐かしい小倉朗氏の「ホタル」が見事にハモり,ちゃんとエコーの様にきこえたのがとてもよかった。このように最近のコーラスはビブラートをかけない人達が増えてきた。とても良いことだ。二期会コーラスや東京混声合唱団もぜひそうして欲しい。でないと,プロと称するコーラスだけが濁りきった叫び合い集団になってしまうだろう。
プーラ・ボーチェにはカノン(輪唱)の指導コーナーまでお付き合い頂いて大変面白い会になった。
ピアノ系が抱く大誤解
やや時間オーバーし質問コーナーをすっとばした為,終ってから沢山の質問が文書で寄せられた。結果,純正律に対して一般の人達が陥り易い誤解に1つの共通項がある事に気づいた。これは,いま私が行っている桐朋学園短大の「純正律講座」でも同様である。そこで,詳しい方にはまたかと思われそうだが,おさらいの意味でも,その誤解を説明しておきたい。
それは,ピアノという楽器への信頼感を打ち破る事に強い抵抗感があるからではないかと思われる。コーラス系からの質問は,どうすればよくハモれるのかといった自然なものだが,ピアノ系の人達の質問は,私が何度も説明しているにもかかわらず「ピアノで純正律に調律できないのですか」とか,平均律は大体ドビュッシー以降の百年間位の歴史しかなく,それ以前には様々な調律の工夫があったと,ミーントーン,ヴェルクマイスター,キルンベルガーについてしつこく説明しているにもかかわらず,「ドビュッシー以前の作曲家やピアニストは純正律だったんですね,じゃショパンの24の前奏曲は演奏できないじゃないですか」という,なんかすがりつくような抵抗感が返ってくる。
玉木版調律の歴史概略
知っている人には自明の理だが,もう一度私なりの調律の歴史の認識を書いておこう。グレゴリアンからルネサンスの初期までは,ピタゴラス音律。そして,長3度の協和を発見した頃から純正律(というか,転調がなければ純正調)に目覚め,ピタゴラス音律用のオクターヴを12分割した鍵盤楽器とどう折り合うかということから,初期のミーントーン(中全音律)が考案された。たくさんの調律法の中で,バッハはヴェルクマイスター第3を使ったとされているという人が多い。またバッハ以前のピタゴラス的ポリフォニーから脱却して,協和の響きを取り戻す為,ヘンデルはミーントーンに戻った。このヘンデルの明快さは圧倒的な影響を与え,モーツァルトは完全なミーントーン主義者だった。そしてベートーヴェンも初期はミーントーンだったが,ヴェルクマイスターを改良したキルンベルガー第3を採り入れて,転調を拡大していった。
キルンベルガー再評価
私は自らコンピュータ上で確認しているが,キルンベルガーは一応全ての調で演奏できる。平均律がはびこる以前は,作曲家,ピアニストの好みで,色々な調律法が使われたと思うが,悪貨は良貨を駆逐するの喩えのように,調律しやすい平均律によって,各調の微妙な色彩感がなくなってしまった。なんだか,栄区の人達の質問に対する回答のような中身になってしまったが,たまには後ろを振り返るのもいいだろう。
現代音楽は1976年に既に死んでいた
ここに1枚のCDがある。アルヴォ・ペルトの「アリーナ」(ECMNewSeries1591, POCC1062/日本発売元:ユニヴァーサル・ミュージック)だ。今日はこの話である。
いわゆる現代音楽といっても,広義には,すべての現在の音楽シーンのことだともいえるが,ここでは狭義の「現代音楽」を話題にする。で,狭義の「現代音楽」とは何か?それは,クラシック系作曲家の現代作品のことを指し,それも親しみ易いメロディやハーモニーを基にした分り易い曲ではなく,難解を旨とする(何回聴いても分らない)不協和音の連続で,大概の聴衆には苦痛を強いるだけのやっかいな曲が多い。
誰が音楽をダメにしたのか
時代は大体,1910年頃から,シェーンベルクが無調音楽(調性のない音楽を始め,ストラヴィンスキーは「春の祭典」で激しいバーバリズムをバレエに持ち込んだ。これ以後,クラシック系の音楽は一挙に様変わりし,シェーンベルクが12音音楽の手法を確立するに至っては,時代は一挙にメロディとハーモニーを放棄した騒音的な音楽が主流となっていった。
そして,1930年代になると,後期ロマン派の生き残りの作曲家も姿を消し,ドテン・バタン・グショーンの無調音楽が全盛となる。当時の風潮としては,分り易い曲を書くと完全にバカにされ,そういう指向の人は,ジャズ系に走ったようだ。
なぜ音楽がそういう風になってしまったのか。一つには,作曲至上主義がはびこり,演奏家より優位に立とうとする作曲家の傲慢が,演奏不能,理解不能の風土を育てた。そしてもう一つは,純正律と平均律の問題が横たわっている。
ピアノ用に簡便な(1回の調律で済む)平均律の調律を施したピアノが工場出荷したのが1842年といわれ,それでも最初のうちは,プロからは全く無視されていた。オクターヴ12鍵のピアノに対し,前期ロマン派の作曲家たちは,ヴェルクマイスター,キルンベルガー等の不等分調律を駆使して作曲していたが, 1890年頃から,プロの作曲家,ピアニストたちも殆ど平均律に屈するようになる。独学で作曲の研鑽をしていたシェーンベルクは,アマチュアのチェロ奏きだった。つまり,音程を自分でコントロールしなければいけない立場である。ピアノやオルガン等は調律師がピッチをコントロールし,演奏者はピッチに対し,無関心で,無神経である。
シェーンベルクは調性を愛した
平均律の跋扈は,ハモる美しさをないがしろにする。ハモらない調律で調性音楽(これは純正のドミソを基礎にしている)をやる矛盾を,チェロ奏きだったシェーンベルクは猛烈に自覚し,オクターヴを単純に12分割するだけなら,各音に差別のない,つまり調性にとらわれない方法論を考案した。私は,シェーンベルクほど調性を愛した人はいなかったんじゃないかとさえ思う。彼の和声法の本は,驚くべき内容だし,初期の「浄夜」なんて,調性音楽のひとつの頂点だとさえ,いえる。その彼が12音技法を編み出したのは,平均律に対するアンチテーゼではなかったのか。平均律の特長は,後期ロマン派の爛熟した転調多用に対応できる唯一の調律法と認識されたからであり,その転調多用の調律を逆手にとり,ハモることを徹底的に拒否するんだったら,という開き直りで編み出した方法論が,12音(ドデカフォニー)音楽だったのではないだろうか?
このメロディもハーモニーもない無機的な作曲法は聴衆に苦痛を与え,作曲家は孤立していったが,メロディもハーモニーも必要ない作曲法は,才能のない人にも「作曲」といえるまがいものを大量生産させることになってしまった。
実は私も学生時代,無調音楽で作曲していたこともあったが,なぜやめたか,いつから純正律に向かい始めたか等は,以下詳しく述べよう。また,1976年というのは何かというと,アルヴォ・ペルトがピアノソロの「アリーナの為に」を初演した年である。ぜひ,その曲を聴いてみて頂きたい。
1976年における転換
ポストモダンの音楽が純正律系をめざすのであれば,後世,1976年が一大エポックメイキング,大転換の年だったことになるだろう。ひとつには,もちろん,アルヴォ・ペルトの「アリーナのために」が初演された年でもあるが,純正律的にはそれだけではない。1990年代になって爆発的なヒットとなり,世界中で300万枚は売れたといわれる,ポーランドのグレツキの交響曲No.3「悲歌のシンフォニー」が,実は1976年に作曲されていた。また,アメリカでファナティックな純正律運動を行い,一種教祖的な存在であった,ハリー・パーチが死んだのもこの年である。しかし,パーチの存在は死後の後継者の一群の啓蒙によって有名になっていく。もちろんその頃の欧米の現代音楽の主流は,相も変わらず無調,12音の平均律跋扈だったが,パーチの後継者,ルー・ハリスンは 1970年頃からさかんにアメリカンガムラン運動を行っている。今日の作風からは信じられないが,彼はシェーンベルクに師事したドデカフォニストだった。グレツキやペルトたちも若い頃はバリバリ前衛の無調派だったのもおかしい。そのハリスン先生,今年亡くなられた。84歳かな?合掌。
さて,そのハリスンが愛した,アルメニア系の孤高の人ホヴァネスの,オーケストラと鯨による演奏の「神は偉大な鯨を創られた」は,1970年に作曲されている。また,ミニマルミュージックによって無調から逃れようとしたスティーブ・ライヒも1970年代から活躍している。今から見ると,1976年前後から無調世界に決別した作曲家が一挙に増えている。一方,日本はどうだったか。
元凶は無調派の台頭?
戦後の日本の作曲界は混沌としていて,小山清茂のような民族派,芥川氏の社会主義レアリズム,黛・諸井両氏の電子音楽に代表される超前衛無調派がひしめいていたが,時代は無調に凱歌を上げ,武満氏の「ノヴェンバーステップス」が1967年に初演されてアメリカで大評判をとったことが社会的事件風にも扱われた。しかし,この成功が,その後長い間,日本の現代音楽を一色にしてしまい,ポストモダンには目もくれない風潮が,大きい目で見れば,日本の現代音楽を不幸にしたといってもよいだろう。
日本も純正律再生の時代へ
さて,私自身の1976年はどうだったのかというと,コロムビアより,日本初のロックヴァイオリンアルバム『タイムパラドックス』を出して有頂天だったというかなりのズレよう。私自身,学生時代に無調の作曲もしていたが,平均律の音程感覚が身に合わず(純正律を教えない,知らない芸大とも衝突を繰り返しエリートコースとも決別),本線のクラシック界からドロップアウトして山本直純の工房に入り,商業音楽まっしぐら。そんな中でのロックアルバムだったから,私自身もそちらの前衛になるつもりでいた頃に,人づてにエプソンセイコーに呼ばれ,純正律と平均律を弾き分ける「ハーモニートレーナー」と対面したことが,その後の私を変えるキッカケになっている。「ハーモニートレーナー」は,西独から特注を受けたすぐれものの機材で,各鍵盤ひとつずつに-15 セント,+16セントの微調整のつまみがあり,自分の耳で純正律和音を訓練できる機材である。私は学生時代の純正律トラウマに目覚め,いろんなレコード会社に純正律の企画を出したが,もちろん一顧だにされなかった。しかし世の中はホグウッドたちのオーセンティック運動の発展形として古楽の純正律演奏が盛んになりつつあったが,1989年のカラヤンの死,1990年のバーンスタインの死が欧米のオーセンティック運動に火をつけた。私は演奏面での純正律にはもちろん興味があったが,作曲とどう結びつけるかに頭がいかず迷っている時,オランダに立ち寄った日本人の友人からペルトの存在を知ったのが1992年。それから首を突っ込んでみると,欧米にいるわいるわの純正律系作曲家。それらに勇気づけられ,日本で初めて出した純正律のCDが1994年だった。
無調的現代音楽の巨匠,J・ケージが死んだのは1992年。日本での大御所,武満さんは1996年に亡くなった。今,日本の現代音楽は支柱を失い,揺れ動いているように見える。1976年にペルトらによって死亡宣告を突きつけられた平均律無調音楽は,今やっと日本でも再考の時期に入っている。
私は去年の末から邦楽の世界にのめりこみ,今,激しく旋法での作曲にいそしんでいる。ひびきとメロディの再構築である。
黒木朋興のコラム
「純正律」という呼称について
ドの音が鳴る弦を1/2に分けるとオクターヴ上のド、2/3に分けるとソ、3/4でファ、4/5でミが得られ、これら純正律の音程で和音をつくると極めてきれいな響きが得られるというのは、自然倍音列という現象によって説明することができる。ただ、この自然倍音列という現象とそこから得られる純正律とは、言ってしまえば、単なる物理現象にすぎない。重要なのはこの現象を前に、様々な人がそれぞれに多種多様な音文化をつくり上げてきたということだろう。
その中でもヨーロッパは、世界で唯一、和声の効果を存分に活かした音楽を築き上げ、そしてそのための理論として調性システムを完成させた、と言われる。しかしそのヨーロッパといえども、地域が違い言葉が違えば同じド・ミ・ソの和音を前にしても考えることが微妙に違うようだ。例えば純正律という表現をドイツ語・英語・フランス語で調べてみると、微妙な言い回しの違いの中にそれぞれのお国柄を感じること ができる。ここではフランス語のケースを中心に、その微妙な違いについて考えてみ たい。
早速、平凡社の『音楽大事典』で〈純正律〉の項を引いてみよう。
――純正律 じゅんせいりつ just intonation[英]、reine Stimmung、 naturliche Stimmung[独] (フランス語では直接これにあたる言葉はなく、「アリストクセノス音階」gamme d’Aristoxene、または「ツァルリーノ音階」gamme de Zarlinoなどと呼ぶ) 純正調とも言う〈……〉
アリストクセノスにしてもツァルリーノにしても音楽理論家の名前なのだから、これらのフランス語は彼らの案出した音階という意味であり、従って純正律に正確に対応した表現であるとは言い難い。では本当に、フランス語に純正律を指す表現がまったくないかと言えば、必ずしもそうとは言えない。
例えば、僕が1998年の夏に、パリのラジオ・フランスの中にあるINA-GRMというミュージック・コンクレートのスタジオで開催された作曲の講習会に参加したときのことである。僕がスタジオで、C=1/1、D=9/8、E=5/4、F=4/3、G=3/2、A=5/3、B=15/8、C=2/1という、純正律を振動数の比で表した表を眺めながらいろいろ思案していると、エマニュエル・ドゥリュティという、コンセルヴァトワール・スュペリユールの作曲科に籍を置く当時22歳の若い作曲家が僕の手元を覗き込み、”pas temperee”と呟いたのだ。つまり生のままの、調整[temper]していない(ずらしていない)音階という意味であろう。
そこで「ドイツ語ではreine Stimmung[純粋音階]というけど、フランス語ではこれに対応する表現がないみたいだね」と聞いてみると、「そんなことないよ。gamme pure[純粋音階]とかtemperament pur[純粋整律]とか、みんな言うよ」という答が返ってきた。「だって辞書にgamme de Zarlinoとかgamme d’Aristoxeneとしか載っていないよ」と言うと、彼は目を丸くしていた。どうやらそういう表現を知らないようなのだ。
数日後、今度は50歳を過ぎたと思しき、やはりコンセルヴァトワール・スュペリユールの作曲科の教授でもあるヤン・ジェスランに「英語でjust intonation、ドイツ語でreine Stimmungというのがありますよね。フランス語では何というのですか」と聞いてみたところ、「えーと、確か、juste, juste……」と言って答に詰まってしまった。もちろん、彼にしたところでメルセンヌやラモーの国、フランスが誇る最上級の音楽学校で作曲を教える人物である。純正律という現象を知らないわけではないのだ。
もちろん、彼らの用語に関する混乱ぶりを勉強不足のせいにしてしまうことはできないだろう。
しかしフランス人の作曲家が「純正律」という表現を知らなかったとしても、それは決して彼らの勉強不足のせいではない。フランス語の音楽事典やテンペラメントを扱った学術書を見てみれば、既にそこからして言葉が一定していないのである。
まずマルク・オネゲル編集の『音楽事典:音楽の科学』(1976)を引いてみると、「ピュタゴラスシステムSysteme pythagoricien」「調整されたシステムSysteme tempere」の項に続き、「ツァルリーノシステムSysteme zarlinien」という項が見つかる。ここでは「G.ツァルリーノがこのシステムを開発したのではないが、これが広く用いられるようになったことに関しては多大なる貢献をしている。その主要な特徴は、ピュタゴラスの長3度(81/64)を倍音列のなかの長3度(5/4)に置き換えたことにあり、3つの音(ド-ミ-ソ=4/5/6)による協和音の可能性に道を開いた……」と説明されている。また「フランスでは物理学者の音階、ドイツでは倍音システムの音階と呼ばれている」という記述があることも興味深い。『音楽ラルース』(1987/1993) では、テンペラメントの項の中で、「平均律le temperament egal」、「ピュタゴラ ス整律le temperament pythagoricien」に続き、「ツァルリーノ整律、あるいは 《不等分律》les temperaments zarliniens, dits《inegaux》」として扱われている。
やはりここでも5/4の3度の重要性が強調されているが、les temperamentsという風に 複数形であることからも察せられるように、中全音律やキルンベルガー整律などの古典整律の説明もこの項の中でなされている。
次に学術書を見てみよう。ピエール=イヴ・アスランの『音楽とテンペラメント』(1985)では、ピュタゴラス律を「ピュタゴラスシステム」として説明し、純正律は「英語の《just intonation》からの訳語である」という断り書き付きで《intonations pures》としている。ジャン・ラタールの『音楽における音階とテンペラメント』(1988)では、やはりそれぞれ「ピュタゴラスの音階gamme de Pythagore」、「ツァルリーノの音階gamme de Zarlin」と呼ばれているのだが、「自然音程 Intervalles naturels」という言葉に「正確なjus-tesあるいは純粋なpurs [ 音階]とも呼ばれている」という但し書きがついている。英語、ドイツ語からの影響であろう。そしてドミニク・ドゥヴィの『音楽のテンペラメント』(1990)では、ピュタゴラス律を「ピュタゴラスシステム」としているのは前述の書物と同様だが、純正律には「自然音階gammenature-lle」という言葉が当てられており、箇所によっては括弧をつけて英語のjust intonationという言葉が添えられている。
確かにツァルリーノは長3度(5/4)の可能性を強調してはいるが、彼の時代ではハーモニーといえばまだ音階論の域を出ず、それが1度-3度-5度などによる和音のことを意味するようなるのは、17世紀にメルセンヌやデカルトらが自然倍音を発見し、18世紀初頭にかけてソヴールなどの物理学者が音響分析を行い、そしてそれらの研究の成果を背景としてラモーが数々の和声論を執筆する18世紀以降であることを考えれば、 純正律が〈科学的〉に理論付けされ実用化されたのは18世紀初頭であると言えよう。
その意味で、ドゥヴィが純正律に「自然音階」という用語を当てているのは、「自然倍音harmoniques naturels」との関連であり、適切な選択であると言えよう。
つまり純正律はツァルリーノではなく、18世紀の物理学者達のもとで和声論とともに花開いた音階なのである。
*
自然倍音という現象はデカルトとメルセンヌが17世紀に発見した、と一般に言われる。ではそれ以前の人々の耳に倍音が聞こえていなかったのか、と言われればそうではないだろう。しかし中世の大学で自由7科の1つとして研究された音楽とは、歌声や楽器の音など我々が実際に耳にする音楽というよりも、ムシカ・ムンダーナ(musica mundana)やムシカ・セレスティス(musica celestis)という世界や天体の秩序のことであり、すなわち耳に聞こえない音楽のことだったということに注意したい。
もちろん、耳に聞こえる音楽文化がなかったということではなく、教会にも宮廷にもそれなりの音楽が培われていたのだが、ここで重要なのは中世の諸技芸は〈神〉に対する近さによって厳密に階層分けされており、耳に聞こえる音楽は、聖歌を除き、一般に低い位置に貶められていたということだ。つまり中世の学者にとって重要だったのは、作曲したり演奏すること以上に宇宙を知ることだったのだから、倍音という実際の音響現象は二次的なことにすぎなかったのである。それに対してデカルトやメルセンヌといった哲学者(=科学者)の功績は、耳に聞こえる音響現象を学術的な議論の爼上に上げたことであり、自然倍音の発見ということもそのような知的環境の変化という相のもとに捉えるべきであろう。
つまり、実際には耳に聞こえない音楽を議論にする以上、倍音現象に注意を払わなくても全く問題はないわけだし、具体的な音響現象を観察し始めた以上、倍音が議論の対象として浮上してくるというわけだ。またデカルトの代表的な著作『方法序説』が、当時の学術書としては極めて異例なことにラテン語ではなくフランス語で書かれているということも思い出しておこう。それまで真理に至るためにはラテン語を身に付け論理学や修辞学を学ばなければならないとされていたのに対し、デカルトは〈理性〉を正しく導いていけばフランス語でも十分真理を理解できると考えたのだ。デカルトが〈近代=現代哲学〉の父と言われる由縁である。
それまで教会や大学の中だけで追求されてきた真理を広く民衆に開くきっかけを作り、音楽を机上の論理から人間の感覚に快を与えるものへと開放した、と言えば聞こえは良いが、しかしこのデカルト哲学最大の問題点は、22歳の彼が『音楽提要』において既に言明しているように、「感覚は絶えず欺かれる」としていたことにある。デカルトの生きた17世紀とは、〈この世のすべては疑わしい〉という懐疑主義で理論武装をしたリベルタン(自由思想家)達が〈神〉の存在を辛辣にあざ笑った時代であり、彼の有名な「コギト・エルゴ・スム(我思ウ、故ニ我アリ)」とは、全てが疑わしいこの世における唯一確実な真理なのだし、そして何よりも〈神〉の存在証明だったのだ。
そのような真理に至る彼の思索の道程において「感覚は絶えず欺かれる」という台詞は、リベルタン(=懐疑主義者)達への理論的な防御装置として機能する。つまり、我々は常に欺かれているのだから全てが疑わしく思えてしまうのも当然のことだ、現に学者達は大学の研究室の中で誤謬に継ぐ誤謬を重ねてきたではないか、だからこそ〈理性〉の光を誤謬に満ちた世界に当てることによって確実な真理に至ることが大切なのだ、とデカルトは説いたのである(デカルト自身の考えというより、むしろ後のデカルト主義が掲げた根本原理であると言ったほう良いだろう)。デカルトは確かに大学の研究室から人間の感覚へと音楽を開放しはしたが、その感覚を全面的に信用したのではなく、具体的な視覚や聴覚の上位に新たなる形而上学的概念を設定したのだ。
つまり物事はただ見たり聞いたりするだけではなく、〈魂〉で感じとらなければならない、ということだ。そしてこの〈魂〉に宿り人間を正しく導いていくものこそが、〈神〉が人間に与えてくれた〈理性〉なのである。
モノコルドと呼ばれる弦が1本だけの楽器がある。楽器と言っても、演奏用ではなく音程比の実験のためのものだった。中世の頃から使われてはいたが、自然倍音の発見に続く17世紀から18世紀にかけての時代において、物理学者達はこの楽器に改良を加え、実験室の中での自然倍音の分析に心血を注ぐことになる。例えば、音響学の基礎を築いたと言われるソヴールが有名だろう。やがて、ジャン=フィリップ・ラモーが現れる。
一般に〈光の世紀〉と称されるこの時代において、彼は独自の和声論を展開しフランス和声学の礎を築くとことなる。他の物理学者と同様、ラモーの仕事においても倍音列の分析は重要であり、当然、彼は、現在純正律と呼ばれるシステムについては熟知していた。また1726年には「変化記号が違えば、音の間隔が様々に違ってくる印象を受ける、という指摘をするのは好ましいことである」と言っているのだから、少なくともこの時点ではまさに不等分律の推奨者であったのだ。
ところが1737年の著作において彼の関心がモノコルドによる倍音分析から和声進行のほうへ移っていくのに伴い、こともあろうに平均律支持を表明するに至ってしまう。
どういうことなのだろうか。
ただ1つの音を対象にしてその倍音列をいくら観察・分析したとしても、それはあくまでも音響の研究なのであり、実際の曲作り、つまり音をどのように組み合わせ和声を進行させていくかということに対しては、距離があることは否めない。だいたい倍音を観察するにしても、雑音のしない実験室において均質な材質からなる良質な金属弦を響かせて行われ、更にそのために使われるモノコルドにしたところであくまでも実験用の楽器であり実際の演奏に用いられることはないのだ。また何よりも純正律では使える和音が限られていることを考えても、実用向きではなくあくまでも実験室の中だけの音階である、という感があったことは否定できない。
だから興味の中心を和声の成り立ちから具体的な和声進行に移していったラモーが、純正律ではなくより実用的なテンペラメントを求めたというのも納得のできることではあるだろう。
以上からすれば、ラモーは1737年にかけて思想上の大転回をした、という解釈も可能だ。しかし、実のところ、ラモーの側からすれば回心したつもりなどこれっぽっちもなかったのではないだろうか。つまり、彼の思想には断固とした連続性を見いだすことができるのだ。それを一言で言えば、一見複雑な現象に見える音楽を理性的な秩序のもとに体系付けようとする意志であったと言えるだろう。
つまりデカルト主義者を標榜するラモーにとって、自然現象は全て理路整然とした幾何学的な体系に基づいているべきものであり、しかもその体系は数学でもって解析できなければならない。
ここで、Natureという言葉には〈自然〉という意味と同時に〈本質〉という意味があることに注意したい。〈本質〉とは目の前に広がる風景のことではなく、〈神〉が取り決めた秩序のことだ。たとえ倍音列から得られる音階が不等分なものであろうと、それはあくまでも見せかけの〈自然〉にしかずぎず、〈本当の自然〉は〈目に見えな
い〉ところにあるのであり、そこは理路整然とした幾何学的な世界なのだから、当然平均律こそがその〈自然〉をものの見事に表象している、ということになる。そしてラモーにとって、音楽こそがこの数の秩序が統べる理想の世界を最も良く体現している芸術なのであり、音楽はこの世の知性の全てを握る芸術とならなければならない。
もちろん、この時代においては技術的に現在のような正確な平均律の調律は不可能であり、それはあくまでも理想の領域にある、ということはつまり「絵に描いた餅」にしかすぎなかったということを言い添えておく。
音響現象こそ自然の中に刻み込まれた幾何学に他ならない、というラモーの主張は、やがて、数学という学問が他の科学の基礎となっているように、他の諸芸術に対して基盤となるべき法則を提供するのは、その数学的理性を最も体現する音楽に他ならない、という見解にたどり着く。更にいえば、理論面での説得力を有すると同時に感覚に訴えかけることもできる音楽は、数学を凌駕し、すべての科学の規範となるべきである、という一種「神学」的な見解にも繋がりうることを指摘しておきたい。
そしてラモーは、バス・フォンダモンタルと和音転回の理論の確立により、旋律をはじめとするすべての音楽現象を独自の「幾何学的」和声体系に還元し、近代和声学の礎を築くのである。
このような和声学はやがて19世紀のドイツに受け継がれ、リーマンが機能和声の理論を確立する。
一方フランスはこの時期、音楽に関してはいわゆる停滞期に入るのに対し、さらにドイツでは、医師、生理学者、物理学者の肩書きを持つヘルムホルツが『音感覚論─音楽理論のための生理学的基礎』(1863)を記すに到る。ヘルムホルツはこの著作の中でreine Stimmung[純正律]の美しさの重要性を強調しているわけだが、彼の弟子には「純正調オルガン」を作成した田中正造氏がいるということを指摘しておく。
このヘルムホルツの仕事を受け継ぐのが、『諸民族の音階』(1885)という書物によりセント法を世に広め民族音楽学に多大なる功績を残したイギリス人、ジョン=アレクサンダー・エリスである。彼の功績はヘルムホルツの著作を英訳した(1875)ことにあるわけだが、特に増補改訂第2版(1885)はより多くの世界に広まり、現在の日本においても「調律技術者の必携書」として大きな影響力を保ち続けている。
さて、このエリスであるが、彼はこのreine Stimmung[純正律]に対して、just intonationという訳語を当てている。ここで、フランス語の学術書において純正律を指すintonations puresやgamme naturelleという表現に英語のjust intonationのことであるという但し書きが付いていたことを思い起こしておこう。すなわち、自然倍音列という現象自体は17~18世紀のフランスにおいて綿密に観察されたものであり、その意味でメルセンヌ、ラモーといったフランス人の手によって純正律研究の礎が築かれたことに疑いはないが、純正律という言葉自体は19世紀のドイツで脚光を浴び、その後ドイツ語の著作の英訳を通じて世界に広まった、ということが言えるのである。
フランスから発し、ドイツ、イギリスを通じて世界に広まるというこの図式に関して言えば、純正律の問題に加えて、「絶対音楽」の理念について語っておくことも決して無意味なことではないだろう。簡単に言えば、西洋キリスト教文化においては長い間、音楽をあくまでも詩に従属したジャンルと見なしていたのに対し、そこから
「言葉=テクスト」から切り離し独立したジャンルと認めようと言うのが「絶対音楽」の理念である。既に見たように、ラモーが音楽とその和声論にすべての学芸の規範となるべき法則を見出していたことを考えれば、そこに音楽の自律という「絶対音楽」の理念の萌芽を見て取ることも可能だろう。しかし彼が最も作曲に心血を注いだのは「叙情悲劇」というフランス固有のオペラであった。そしてこの「叙情悲劇」に対立する概念がラシーヌに代表される「古典悲劇」であることを考えれば、ラモーの活動はあくまでも文学の領域に留まるものと見なされる、ということを指摘しておく。
いずれにせよ、17~18世紀にフランスで培われた音楽文化が、現在の我々のもとに届くには、1回、ドイツを経由しなければならなかったのである。
(完)
ミーメーシスについて
ミーメーシスとは何か、という話をします。一見音楽に関係ないかのように思われるかも知れませんが、近代以前の西洋芸術のあり方を理解するためには、是非とも知っておかなければならないことと考えるからです。端的に言えば、ミーメーシスとはギリシア語で「模倣」という意味です。と、こう日本語で訳語を当てると、本物に対して紛い物みたいな感じがして、否定的な印象を拭い去ることが出来ませんが、ミーメーシスとは単なるコピー=複写ではなく、「本質的なるものの再現」と言った方が良いでしょう。更に、芸術がミーメーシスの原理に基づくという時、芸術創作とは「より真なるものをこの世に出現させるための営為」ということなります。
この概念はプラトンやアリストテレスの哲学の中でも重要な位置を占めますし、また西洋人が西洋の伝統という時、古代ギリシアまで溯って考えることが普通なのですが、ここでは古代ギリシア・ローマ文明と現在の西洋文明の間には断絶があるという立場から、あくまでもキリスト教文明を中心に据えて話を進めることにします。もちろんキリスト教に対するギリシア哲学の影響を認めないというわけではありません。
キリスト教思想というのは、基本的に「あの世」と「この世」という厳密な二項対立を想定している、と言っても過言ではないでしょう。当然、「この世」とは我々人間が住んでいるこの世界のことであり、「あの世」とは神の統べる世界のことです。
気を付けて欲しいのは、日本語で「あの世」と言えば魑魅魍魎の跋扈する何だか妖しげな世界のことを思い浮かべる人も多いことかとは思いますが、キリスト教にとっての「あの世」とは物事が理想的なまでに理路整然としてある「本質」の世界です。キリスト教の神とは、ロゴス=理性・言葉の神であることを思い出しておきましょう。
そして芸術の役割とは、「あの世」の理想的な美を「この世」の人々に提示することなのです。あるいはそのような美を「この世」において「再現」しようと務めることに芸術の価値があるということでもあります。
でも一体この「本質」とはなんでしょう?ここではbe動詞のことを考えてみましょう。そもそもbeとはどういう意味でしょうか?まず最初に挙げられるのが「いる・ある」という意味です。例えばThere is a pen.(ペンがあります。)という例文が考えられます。つまりexistenceの意味であり、この語は「存在」とか時には「実存」とか訳されます。それに対して、This is a pen. のbeはどういう意味でしょう?
多くの人が「です」と答えるのではないでしょうか?学校でそう教わるのですから仕方がないのですが、かなり不適切な訳であると思っています。では何かと言えば、このbeはイコールなのです。ですからこの文は「これ=ペン」ということになり、これを普段我々が使っている日本語で言うと「これはペンです。」あるいは「これはペン。」という意味になるというわけです。さて、このbeはラテン語で何に当たるかというと、esseになります。そしてこのの名詞形がessenceであり、つまり「本質」 です。この「本質」目指してイコールで結んでいく論理の体系のことを神学といい、 また暗喩という文彩はイコール関係に基づくレトリックだと言えましょう。
「この世」は不完全です。ですが、というかだからこそ、学問なり芸術は、たとえ手にしているのが不完全な材料ばかりだとしても、それをどうにかしてでも組み合わせて「本質」の世界へと迫らなければなりません。つまり「この世」と「あの世」の間のイコール関係、あるいは照応関係を探る営みこそがミーメーシスであると言えましょう。
では次にこの2つの意味が混同されて用いられた場合に引き起こされる問題について考えてみましょう。
例えば、幽霊やUFOがいるかいないか、という議論があって、テレヴィなどでも賛成派と反対派に別れて論争を繰り広げる、といった番組が時々放映されます。しかし、ほとんど言って良いほど、この手の議論は決着がつかず、終いには喧嘩になって終わってしまいます。口に泡を飛ばしている当事者の方のほとんどが意識していないこととは思いますが、このような場面で生じる議論のずれといったことは、まさしく「本質」と「実存」の間の問題なのです。つまり、「いる」という賛成派が「本質」の、対し て「いない」という反対派は「実存」の議論をしている、ということです。
賛成派の人々は「いる」ことの根拠として、「この私が直接見た、あるいは直に体験した」ということを挙げます。そしてそのことの証明のために、写真を取ったりヴィデオを見せたりします。そうして「自分が体験したこと」を熱く説明します。この説明とはどういうことなのかについて考えてみましょう。これは「自分が体験したこと」という事実なり真理をイコールで繋いでいくという行為である、とは言えないでしょうか。例えば、現実に起こったことと写真なりヴィデオの内容が完全にイコールで結ばれるのなら、証明は成功したことになります。ところが反対派は写真なりヴィデオなりはあくまでも複製だからと言って、つまり二次的なものに過ぎず事実そのものではないと言って否定します。時には「インチキだ!」とか、「後から手を加えてあるはずだ!」とかも言ったりします。ですから賛成派は今度は言葉を使って懸命に、修正などは一切していないことを、自分は嘘などついてはいないと言い出します。すなわち、彼等の説明においてはイコールの整合性が焦点となっているわけです。その意味で、彼等は「本質」の議論をしていることになります。対して、反対派は何を言われても、何を見せられても、信じません。何故なら彼等は端からイコールの部分など見ていないからです。彼等が問題にしているのはあくまでも「実存」で、そんな「いかがわしいもの」は最初から「実存」しないと言っているのです。最終的に賛成派は「オレは嘘などついていない。このオレが信じられないのか!」などと言い始めます。
対して反対派は「自分がうまく証明できなかったことを棚にあげて、何を言い出すか!」と切り返します。こうなってくると興奮が興奮を刺激し、単なる罵り合いへと落ちいきます。
同じテーマを議論しているにもかかわらず、片方は「本質」の、そしてもう片方は「実存」の話をしているのでまったく議論は噛み合わないのですが、深刻なのは、多くの場合、当事者達がこのずれを意識していないということです。これが幽霊とか宇宙人に関する議論であればまだ可愛いものでしょう。しかし「民主主義」とか「神」とかであったらどうでしょうか?笑い事ではすみません。何故なら未だもって人類は、この種のテーマで議論をこじらせ、時には殺し合いまでしてしまうからです。
西洋の言語の特長は、この「本質」と「実存」を同じ動詞でもって表せることだ、と言っても過言ではないでしょう。このことは神学を始め、哲学・文学・芸術など、キリスト教文化のすべての基礎となっています。対して、我々の日本語には、イコールの意味を持つ動詞はありません。実は旧約聖書の言葉、ヘブライ語にもやはりない そうです。ここで新約聖書はイエスの死後、ギリシアの信徒によってギリシア語で書かれた、という事実を確認しておきましょう。つまりイコールの意味の動詞を持たないヘブライの民の宗教とそれのあるギリシア哲学の出会いこそが、ヨーロッパキリスト教文化の礎を形成した、ということです。
今までの議論をまとめれば、「本質」の探求とは「あの世」と「この世」を「=」 で繋いでいくことなのに対し、「実存」のほうは「いまここにある」物事だけに焦点 をあて、この「ある」ということがどういうことかを分析していくことだ、と言えるでしょう。
「『実存』は『本質』に先行する」。言わずと知れたサルトルの有名な台詞です。実存主義が流行った時代には、様々な解釈が試みられ、それぞれがそれぞれの思いをこのフレーズに投影していったようではありますが(それが必ずしも悪いことではないと思います)、今まで述べてきた「本質」と「実存」の話にこの台詞をおいてみれば、サルトルの真意が何とはなしに見えてくるでしょう。つまり、「神」を中心に据えた思想体系への彼特有の反抗の念がこの台詞には込められている、ということです。
「神」の国にある筈の理路整然とした美しい「真理」、あるいは、「あの世」を持ち出すのがいかがわしいというのなら今ここ目の前にはないけれどどこかには必ずあるだろう完璧な「美」、これらを模倣しようというのがミーメーシスの原理であるということは前々回見た通りです。モダン以前における芸術の役割とはまさにこの「理想」をこの世の人々に提示することであった、ということも良いでしょう。そして、この「理想」と「現実」の従属関係を断ち切り、ひたすら今ここ目の前にある物質に焦点を当て、そのある姿を分析していくのが実存主義ということになります。また、理想の美を目指すのではなく、自らの感性を便りにこれらの物質を組み合わせ作品を創っていこうというのが19世紀末フランス象徴主義以降のモダン芸術のあり方でもあるわけです。
ただし気を付けておきたいのは、このようなミーメーシスの原理を超克しようとする発想は、実のところ、18世紀末から19世紀初頭にかけて初期ドイツロマン主義者達の間で夢見られたということです(もちろんこの発想の源流はフランス18世紀ルソーや17世紀のボワローまで溯ることも可能でしょうが)。彼等は当時盛んに作曲された交響曲の響きにその夢を投影します。あるいは彼等の理論は純粋器楽作品の開花という実際の現象に支えられている、とも言えるでしょう。当然、ここで俎上に上がっているのは、「絶対音楽の理念」のことです。「絶対音楽」とか「純音楽」とかいうと、人それぞれにいろいろと思うところもあるでしょうし、実際いろんな解釈が可能だとは思いますが、最も重要なのは、この理念が芸術をミーメーシスの原理から切り離し解放しようとした、ということです。こう書くと何やら難しそうですが、何のことはない、音を「神」、宇宙、真理や感情など他の概念の比喩・暗喩として捉えるのではなく、音を音として、モノをモノとして扱う、ということです。僕らのようにキリスト教徒でないものから見れば当たり前に思えることですが、長い間西洋キリスト教の世界では、芸術の役割とは真理の模倣(ミーメーシス)であり、このことが彼等の文化の強力な特徴をなしてきたということを再度確認しておきましょう。
ここで「絶対音楽」の唱道者として名高いハンスリックの一節を引用してみたいと思います。
「一枚の歴史画においてあらゆる赤が喜びを意味したり、あらゆる白が潔白を意味するとは限らぬと同様。一つの交響曲においてすべての変イ長調が熱中的気分を、すべてのロ短調が厭人的な気分をよび起こすというわけではない。あらゆる三和音が満足をあらゆる減七和音が絶望をよび起こすというわけではない」(『音楽美論』、渡辺護訳、pp.42-3.)
例えば「メジャーキーは〈楽しい感じ〉、マイナーキーは〈悲しい感じ〉がするという意見があるが、どうかと思う。メジャーキーはメジャーキーを、マイナーキーはマイナーキーを表現しているだけなんだ」と言う人がいますが、つまり、このような見解はまさに「絶対音楽」の延長線上にあるものだと言えるのです。もちろんここでは、この見解が当たっているか、間違っているかということを問題にしているわけではないということを言い添えておきます。
(続く)